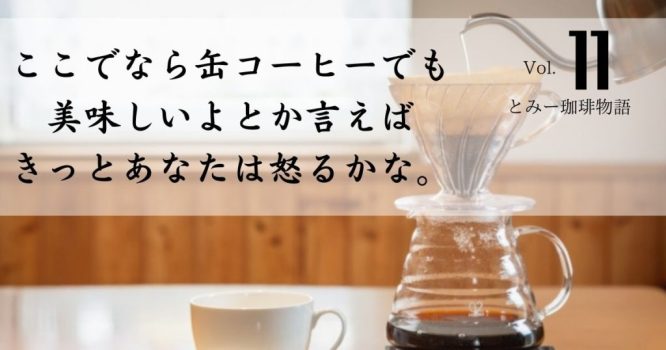「うん、美味しいよ」
口紅の付いたカップを置きながら、唯実(ゆみ)は笑う。
「当たり前だろ。俺が淹れたんだから」
唯実の言葉を受け、テーブルを挟んだ向かい側に座る男は、自信たっぷりに言い放つ。しかし言葉とは裏腹に、その声色には、ほっとしたようで、嬉しそうな感情が滲んでいる。
あまりある自信と期待と、ちょっぴりの不安。
なにかをつくり、それをだれかに受け取ってもらうときの気持ちというのは、みんな似たようなものなのだろう。
その気持ちは、唯実にもわかる。
「だね。伴貴(ともき)のつくる珈琲は、美味しいよ」
唯実はそう言うと、また一口、カップの縁についた紅を、深くする。そうやって唯実が珈琲を飲むたび、伴貴は満足そうに頷く。
窓から吹き込んだ風が、ふたりの前髪を揺らす。
大学生に上がって互いが一人暮らしの部屋を持つようになってから、こういった時間を、唯実と伴貴は頻繁につくっている。
唯実は、この時間が好きだった。
「それも、ただの珈琲じゃないぞ。俺が淹れるのは、スペシャルティ珈琲だけだからな!」
ベッドに冷蔵庫、洗濯機に電子レンジ。男の子ひとりが生きていくのに必要最低限の物しか置かれていない、淡白なワンルーム。
そんな部屋で、ひと際異彩を放つのが、でかでかと置かれた、珈琲の焙煎機。
伴貴は大学生になって、夢を持った。いつか自分のブランドで珈琲店をやるという、立派な夢だ。だからこうして人に試作のブレンド珈琲を振舞うことも、夢を叶える為に必要なことなのだと言う。
唯実は幼馴染のそんな夢を、心から応援していた。
「俺は俺の珈琲で、多くの人に、スペシャルティ珈琲の魅力を伝えたいんだ!」
入学してからしばらくは唯実の部屋で集まる頻度の方が高かったが、伴貴が自室で珈琲の焙煎をするようになってからは、唯実の方がお呼ばれして自作のオリジナルブレンド珈琲を振舞ってもらう、という形が主流になった。
部屋の隅に寄せられた小さな本棚にも、小説や文芸の類は一切なく、珈琲関係の本ばかりが並べられている。
──きっと、興味ないんだろうなぁ。
伴貴の淹れてくれる珈琲はほんとうに美味しい。たぶん、唯実以外のだれが飲んでも、そう感じると思う。
現に、伴貴は大学が休みの日に、たまに地域のイベントで出店をさせてもらっているらしい。本格的な珈琲だと、なかなか好評なようだ。
──でも。
心臓の部分がすこしざわつくのは、珈琲の飲み過ぎによるものではないだろう。
「スペシャルティ珈琲ってさ、なんか大げさな言い方じゃない?」
「なんだよ、大げさって」
あくまで笑いながら、冗談めかしたように、唯実。カラカラと喉が渇く。心臓のざわつきは収まらない。
怪訝になった伴貴の顔から目を背けるようにして、珈琲をもう一口飲む。
美味しい。
「だって、スペシャルって言っても……それは、良い豆を使ってるってだけでしょ?」
伴貴の顔は見れないまま、もう一口。
美味しい。
伴貴はきっと、自分のつくるものを信じられる人間だ。自分が淹れる珈琲で他人を喜ばせることができると、信じ切れている人間だ。
だからこうやって、他人に珈琲を振舞うことができる。
──わたしなんかとは、持ってるものがちがいすぎる。
唯実の心臓のもやもやは、暗さと重さを増していく。カップのなかの珈琲のように。
もう、冗談めかす余裕もなくなっていた。
「そりゃあ、豆が良かったら、珈琲も美味しくなるよね」
もとの素材が良ければ、結果が良くなるのは当然だ。
この世の中は、才能さえあれば、うまくいくようにできている。逆に、才能がなければ、何者にもならない。唯実が大学生になって、親元を離れてみて学んだのは、そんな残酷なリアルだった。
伴貴にはきっと、才能がある。
だから唯実は、伴貴の淹れてくれるこの珈琲を飲むことが、たまらなく──
「なに言ってんだ唯実!」
伴貴の声に、びくっと身体を震わせる。そこで思考の底から意識が戻ってきて、自分が言わなければいいことを、つい口に出してしまったことを、唯実は知る。
「唯実、おまえ」
恐る恐る顔を上げると──目の前の伴貴は怒るでも悲しむでもなく、ただ呆れたような顔をしていた。
「スペシャルティ珈琲のこと、なにもわかってないな。こんなに飲んでるのに」
「へ?」
「お前が言っているのは、一般的な珈琲の品質基準の話だ」
伴貴は小説も漫画もない本棚から、一冊の分厚い本を取り出す。珈琲のことが、たくさん書いている本だ。付箋がたくさん貼られ、所々がしわくちゃになっている。伴貴はきっと、これを使って勉強していたのだろう。
ページを捲ってみる。すると伴貴の言うとおり、一般的な珈琲は、生産地の標高や粒の大きさ、欠点豆の混入率で本質を分けられる、と書いてあった。
「一般の珈琲は、そういう“生産者だけ”の都合で品質が判断されてるんだよ。だから、その珈琲が絶対うまいって保証はない」
そう語る伴貴の顔からは、すでに呆れの色も消えていた。もう、唯実のことが視界に入っているかすら危うい。
好きなものを語る彼の顔は、ただただ、楽しそうだった。
「対してスペシャルティ珈琲はな、カップクオリティ──抽出した珈琲がどれだけ美味しいか、ってとこを基準に考えてるわけ。そりゃあ、実際に飲むお客様からしたら、大事なのはどんな品質の豆を使ってるかよりも、その珈琲が美味しいかどうかだからな」
徐々に熱を高めて、早口で捲し立てる伴貴。
──ほんとうに、珈琲が好きなんだなあ。
その様子を見て、羨ましいなあ、なんて、唯実は考えてしまった。
唯実はずっと、伴貴のことが羨ましかったから。
「スペシャルティ珈琲の品質の判定方法には、大きく七種類あってだな──」
昔はよかった。夢を持つことも、お金を稼ぐことも、社会は幼い彼女たちになにも要求してこなかった。
小さい頃は、それはもう、ふたりとも珈琲なんて飲めるような舌をしてはいなかった。おままごとやヒーローごっこで遊び疲れたら、並んで仲良くオレンジジュースを飲んだものだ。
夢を追うことは、苦くて、苦しい。
まるで珈琲を飲んでいるかのよう。
子供に飲めるようなものじゃない。
「あと、甘さも大事だな。あ、糖分量の話じゃないぞ? 糖分以外にも、甘さの印象を作る要素や成分ってのはあってだな──」
夢を実現しようとすることは、もっと苦い。
でもいつのまにか、伴貴は苦さのなかにある、甘さや酸味を知ってしまった。だれかに喜んでもらえる嬉しさや、一生懸命挑戦することの尊さを、ちゃんとわかってしまった。
苦さのなかにあるものが、苦しみだけではないことに、気付いてしまった。
「酸味の質も重要な判断材料で──口に含んだ質感とか──」
実際に行動に移したからこそ触れられる、たしかな質感。伴貴は日々のイベント出店で、多くの人を喜ばせようとしてきた。
──それに比べて。
勘違いしていた。良い豆を使った珈琲が、スペシャルティ珈琲だというわけではなかった。持って生まれたものを、ちゃんと活かせているか、どこまで磨き上げたか。問われていたのは、そのクオリティだ。
天才が胡坐をかける世界じゃないし。
幼馴染だけが、彼の隣にいていいわけじゃない。
唯実は、伴貴から渡された本を、強く握り込む。しわくちゃのページと貼られた付箋の数が、彼の努力を物語っていた。
「──後味の印象や、バランスも──」
「ねえ、伴貴。ひとつ、聞いてもいいかな?」
「なんだ⁉ なんでも答えるぞ!」
昂って鼻息を荒くする伴貴。その熱量から逃げるように、唯実は冷たくなったカップに口をつける。珈琲は温度によって違った味わいを見せる。時間経過によって、楽しみ方を変えられるのだ。
「もしもさ、そうやって一生懸命がんばってつくった珈琲がさ、その……お客様にとって、あんまり美味しくなかったとして」
「俺が淹れる珈琲はうまい!」
「もしもだよ。もしも、万が一にも、あんまり美味しくないものをつくっちゃったとしてさ……伴貴なら、どうする?」
唯実は手元の本と、小さな本棚に、目線を移す。
もしも一生懸命がんばって、思い通りの結果が出なかったら。
それは好きなものを手放す理由には、ならないだろうか?
きっとこんなこと、これまで頭に過りもしなかったのだろう。伴貴はしばらく天井を仰いでから、こう返した。
「そのときは、もっと美味しい珈琲を淹れられるようにする! そんで、そのお客様にも満足してもらう!」
それから、唯実に向き直って、力強く言い放つ。
「だって、それがスペシャルティ珈琲のバリスタだから!」
その言葉を聞いて、唯実の心に拡がるもやもやは、罪悪感へと形を変える。先刻、自分が言ってしまったことを思い出し、ひどく後悔した。
──スペシャルって言っても、良い豆を使ってるだけでしょ?
わたしは、なんてことを言ってしまったんだろう。気付けば、唯実の視界はぼんやりと滲んでいた。
「ごめんなさい……」
唯実の目に、涙が溢れる。
「ど、どうした? なんで泣くんだ? まさか、俺の珈琲、ほんとはまずかったんじゃ……」
「ううん、美味しかったよ。ごめんなさい……わたし、スペシャルティ珈琲のこと、なにも知らないのに……わかったようなこと言って……」
「いや、べつにそんなの知らなくてむしろ当たり前っていうか、泣くようなことじゃ……」
幼馴染の突然のガチ泣きに、熱も冷めてきたようで、おろおろとする伴貴。
しかし唯実の目から落ちる涙は止まらない。透明な雫は、ぼたぼたと、分厚い本のなかに滲んでいく。
──わたし、スペシャルティ珈琲のことも……伴貴のことも、なんにもわかってないのに。
涙の雫は、カップのなかにも落ちてしまう。
せっかく焙煎して、抽出して、淹れてくれた珈琲の味バランスが変わってしまう。唯実は落ち込みと焦りで、さらに涙が溢れてくる。
──ほんとにほんとに、ごめんなさい。
「謝る必要なんてない
よ、唯実」
頭の上に手が置かれた気がして、唯実が顔を挙げると、伴貴がすぐ傍にきていた。
「さっきはテンション上がってぺらぺら語っちゃったけど。本来スペシャルティ珈琲がどうだの、ってのは、飲む側が気にするようなことじゃないんだ」
冷めてもうまいだろ、と、伴貴はカップを、唯実の口元まで持ってくる。
「お客様が、なにも考えなくても美味しい、最高品質の珈琲を嗜むシチュエーションを提供する。それだけが、俺の仕事だから」
「……うん。美味しいよ」
唯実はまた、カップに口紅をつけ、吐息を漏らす。それを見て、伴貴は満足そうに笑いながら、頷く。
窓から吹き込んだ風が、涙をさらい、珈琲の水面を揺らす。
唯実は、この時間が、伴貴の淹れたこの珈琲が──
ふたりだけのこの空間が、大好きだ。
「ね、ねえ、伴貴。よかったら今度、わたしが書いた小説、読んでみてほしいんだ──」
「お、小説⁉ 唯実、本とか好きだったもんな! もちろん読ませてくれ! 読書と珈琲は相性が良い! あ、なんなら、珈琲の物語とか書いてくれよ──」
完。
\ スペシャルティコーヒーを飲んでみよう/